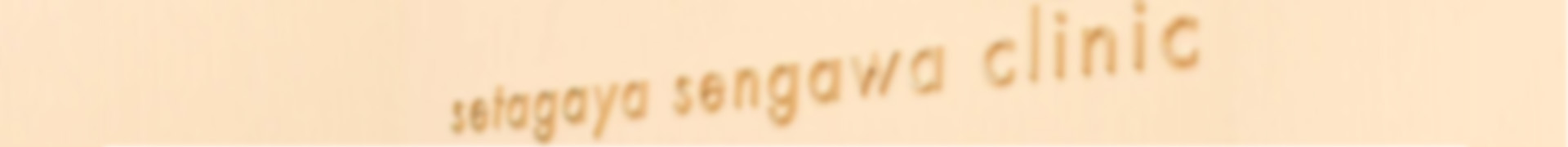バセドウ病(甲状腺機能亢進症)
甲状腺ホルモンには、全身の臓器に作用して体の発育を促進し、新陳代謝を盛んにする大切な働きがあります。この甲状腺ホルモンは、多すぎても少なすぎても体調が悪くなります。バセドウ病は、甲状腺ホルモンを過剰に産生する病気で、代謝が高まる(亢進する)ことで様々な症状が現れます。
典型的な症状としては、暑がりになり汗をかきやすくなったり、手が震えたり、体重減少、動悸などが現れます。下痢、気持ちが落ち着かない、怒りっぽくなる、疲れやすいなどの症状を伴うこともあります。女性では生理が止まることがあります。男性によくみられる症状には、炭水化物の多い食事の後や運動後などに手足が突然動かなくなる発作(周期性四肢麻痺)があります。
のどぼとけのすぐ下にある甲状腺は、全体的に大きく腫れてきます。眼球が突出して、周りの人に指摘されたり、目が完全に閉じなくなったりすることもあります。
治療は大きく分けて、薬物療法、放射性ヨウ素内用療法、甲状腺摘出術の3つがあります。多くの場合、まず、抗甲状腺薬による薬物療法が行われます。薬物療法を2年以上継続しても薬を中止できる目途が立たない場合には、放射性ヨウ素内用療法や甲状腺摘出術などの他の治療法が検討されます。
バセドウ病はストレスによって病気が悪化したり、再発したりすることがあるので、日常生活では、できるだけストレスを避けて規則正しい生活を送るように心がけましょう。
橋本病(慢性甲状腺炎)
橋本病は慢性甲状腺炎ともよばれ、甲状腺ホルモンが少なくなる病気の代表的な疾患です。日本人で頻度が高く、成人女性の10人に1人、成人男性の40人に1人にみられます。ただし、すべての患者様で甲状腺ホルモンが少なくなるわけではなく、橋本病のうち甲状腺機能低下症になるのは4~5人に1人未満といわれています。30~40代の女性に発症することが多い疾患です。
橋本病は免疫の異常により炎症が生じ、甲状腺が少しずつ破壊されます。甲状腺の炎症により首が太くなったようにも感じます。症状としては、全身の代謝が低下するため、耐寒性の低下(寒がり)、体重増加、体温低下、だるさ、かすれ声、便秘、高脂血症などが出現します。女性では月経過多になることがあります。また、気分が落ち込んだり、不安感が増したりすることもあります。うつ病や更年期障害、脂質異常症として治療されていることもあるので、疑わしい症状があれば、甲状腺ホルモンの検査をお勧めします。
甲状腺の機能低下(甲状腺ホルモンの減少)がみられない場合、原則的に治療は必要ありません。甲状腺機能低下症が認められる場合は、合成T4製剤(甲状腺ホルモン薬)の内服を行います。昆布など海藻類に多く含まれるヨウ素の過剰摂取は、甲状腺の働きを低下させるため、過剰摂取が疑われる場合は、ヨウ素制限も必要となります。
倦怠感など甲状腺機能低下症の症状が強い場合、治療によって甲状腺ホルモンが正常に戻るまでは、あまり体に負担をかけないように心がけましょう。
甲状腺腫瘍
甲状腺腫瘍は無症状のことが多いため、頸部のしこりに偶然気づいたり、検診などで指摘されたりする方が増えています。多くは良性腫瘍であり、腺腫様甲状腺腫(せんしゅようこうじょうせんしゅ)、濾胞腺腫(ろほうせんしゅ)、のう胞などが含まれます。悪性腫瘍(甲状腺がん)は、乳頭がんが全体の90%以上を占めているといわれています。甲状腺に腫瘍がみつかった場合、まず、超音波検査を行い、悪性が疑われれば、精密検査として穿刺吸引細胞診を実施して良悪性を鑑別します。
腫瘍が大きい場合、甲状腺のしこりや甲状腺全体に腫れが認められます。前頸部に違和感などを生じることもあります。腫瘍から甲状腺ホルモンが過剰産生される機能性甲状腺結節では、動悸や発汗過多、体重減少などがみられることがあります。
良性腫瘍であれば、原則的に経過観察となりますが、腫瘍が大きく圧迫症状が強い場合や美容上気になる場合、あるいは悪性腫瘍の合併が疑われる場合などは手術を検討します。悪性腫瘍の治療は手術が基本です。術後再発や遠隔転移がある場合は、手術後に放射線ヨウ素内用療法が行われます。
甲状腺腫瘍は、当初、良性と思われていた腫瘍が、経過とともに悪性の可能性が高まってくることがありますので、良性と診断されたとしても経過観察は必要です。とくに経過中に大きくなってくるケースは要注意です。
腺腫様甲状腺腫
甲状腺にしこりができる病気のなかで最も頻度の高い疾患です。結節が多発した状態を「腺腫様甲状腺腫」、結節が単一のものを「腺腫様結節」といいますが、病態は同じです。甲状腺の細胞が増えたり、壊れたりしながらしこりを形成します。良性ですので圧迫感などの強い症状や美容上で問題がなければ、手術はせずに経過観察となります。長期の経過の中で、結節が自律性に甲状腺ホルモンを産生し機能亢進状態になる「中毒性多結節性甲状腺腫」に移行することもあります。この場合、状況によって薬物療法(抗甲状腺薬)、手術、放射性ヨード内用、経皮的エタノール注入療法(PEIT)などを選択します。
亜急性甲状腺炎
甲状腺に炎症が起こり、甲状腺組織が壊れる病気で、炎症による症状と甲状腺ホルモン高値(甲状腺中毒症)による症状が伴います。炎症による症状には、発熱、甲状腺の腫れ、強い痛みなどがあり、甲状腺ホルモン高値による症状には、全身倦怠感、動悸、多汗などがあります。風邪の後に続いて起こることがしばしばあり、ウイルス感染により生じる可能性があります。
時間はかかるものの自然に炎症や甲状腺中毒症は治まりますが、高熱や首の痛みがひどい方では生活に支障を生じるため、症状に応じて副腎皮質ホルモン(ステロイド)や抗炎症薬の投与が必要となります。ステロイドの内服で症状はおおむね改善しますが、急に内服を中止すると、ぶり返してしまうことがあるので、症状改善後は薬を少しずつ減らし、中止します。