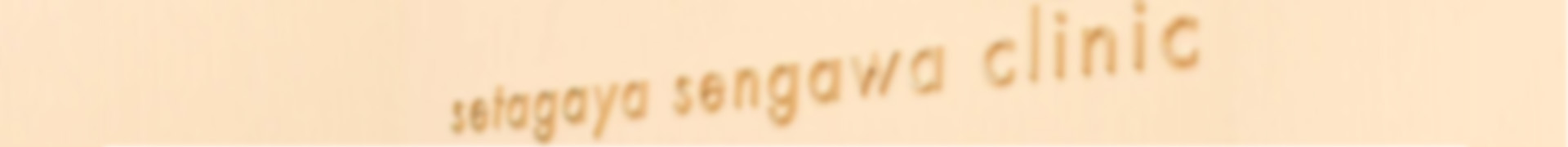
高血圧
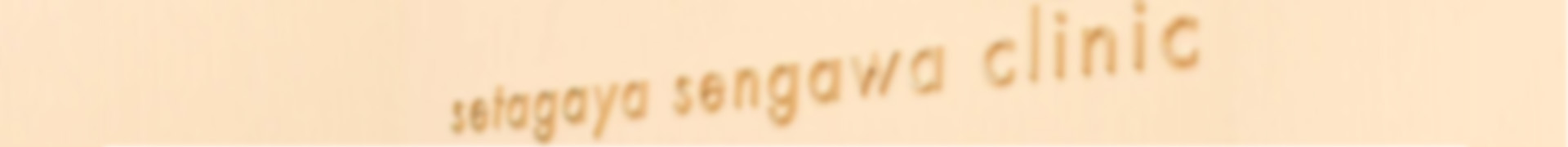
高血圧

高血圧とは、血圧が慢性的に正常範囲より高い状態を指します。血圧は心臓が血液を血管に送り出すときにかかる圧力のことで、通常「収縮期血圧(上の血圧)」と「拡張期血圧(下の血圧)」の2つの値で表されます。 日本高血圧学会による高血圧の基準は以下の通りです。
| 分類 | 収縮期血圧(mmHg) | 拡張期血圧(mmHg) |
|---|---|---|
| 正常血圧 | 120未満 | 80未満 |
| 高値血圧 | 120~129 | 80未満 |
| 高血圧(Ⅰ度) | 130~139 | または 80~89 |
| 高血圧(Ⅱ度) | 140以上 | または 90以上 |
この基準は医療機関での測定に基づき、家庭での測定ではやや低めの基準が適用されます。
高血圧の診断や治療には、単に血圧を測るだけでなく、「なぜ血圧が高いのか」や「高血圧による臓器障害や合併症の有無」を総合的に調べることが重要です。主な検査は以下のとおりです。
医療機関で測定しますが、緊張などで実際より高く出る「白衣高血圧」の可能性があります。
毎日朝晩決まった時間に測ることで、より日常の正確な血圧傾向が把握できます。
血液検査では、腎機能(クレアチニンやeGFR)、血糖値やHbA1c(糖尿病の確認)、脂質(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)、電解質(ナトリウム、カリウム)、肝機能などをチェックします。
尿検査では、尿タンパクや微量アルブミン尿を調べ、腎臓の障害の早期発見に役立てます。
心肥大、不整脈、虚血性心疾患の兆候がないかを確認します。
心臓の大きさや肺の状態を確認し、高血圧による心肥大などの兆候を調べます。
腎動脈の狭窄や腎臓の異常を確認し、二次性高血圧(原因が明確な高血圧)を発見するのに役立ちます。
高血圧が長期にわたると血管や臓器にダメージを与え、重大な合併症を引き起こします。特に影響を受けやすい臓器は脳、心臓、腎臓、眼、血管です。以下に主な合併症を臓器ごとにまとめます。
網膜の血管が障害され、視力低下や最悪の場合失明のリスクがあります。眼底検査で早期発見が可能です。
これらを継続的に行うことが重要です。
高血圧の治療目的は、血圧を正常範囲にコントロールし、合併症の発症や進行を防ぐことです。主に生活習慣の改善と薬物療法の2本柱で進められます。
生活習慣の改善だけで十分な血圧低下が得られない場合や合併症リスクが高い場合に開始されます。
主な降圧薬は以下の種類があります。
薬の選択は患者の年齢、合併症の有無、体質、他の持病などにより異なり、複数の薬を組み合わせることも多いです。副作用の管理と定期的なフォローアップが欠かせません。
高血圧は、血圧が正常より慢性的に高い状態であり、心臓や血管、腎臓、脳、眼など多くの臓器に悪影響を及ぼします。血圧をコントロールしないと、脳卒中や心疾患、腎不全などの重篤な合併症を引き起こすリスクが高まります。
診断には正確な血圧測定とともに、血液検査や心電図、レントゲン、超音波検査などで原因の特定や臓器障害の有無を調べることが重要です。
治療は生活習慣の改善を基本とし、必要に応じて薬物療法を組み合わせます。減塩、適度な運動、体重管理、禁煙、節酒、バランスの良い食事、ストレス管理を心がけることが大切です。
また、定期的な検査と医療機関でのフォローアップを受けることで、合併症を未然に防ぎ健康な生活を維持しましょう。
